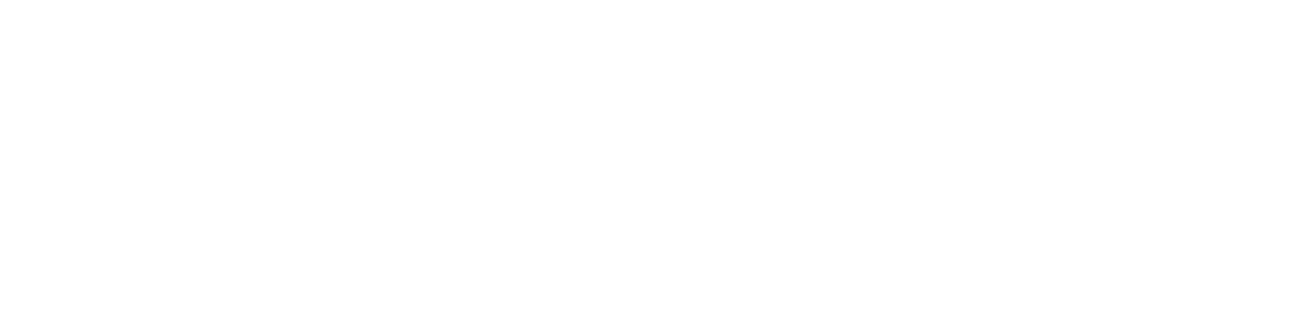無縁仏とは?
代々引き継がれてきたお墓も、子供がおらず継承ができなくなる事例が増えています。
無縁仏とは、亡くなった後に引き取り手のないご遺体やお骨、守る人がいなくなったお墓のことを言います。
墓地においてはお墓の持ち主となっている施主が亡くなった後に引き継ぐ人がいなくなったお墓や、墓地の年間管理費を何年も支払われず連絡も取れない状態で実質的に管理する人がいなくなったお墓のことを無縁仏や無縁墓と言われることがあります。
継承し管理する人がいなくなったお墓は、風雨にさらされ続け時間の経過とともに劣化していきます。
傾いたり崩れたりして、時に周囲のお墓や参拝者に危険を及ぼしかねない状態になることがあります。

無縁仏の状態になってしまった時、墓地の管理人はどのように対処するのでしょうか。
墓地管理者が出来ることと必要な手続き
無縁仏となったお墓は、一定の手続きを経た後に、墓地の管理者により改葬、つまり解体・取り壊しをすることができます。
現況図を作成し、写真等の記録を残す
墓地全域への改装公告看板の設置
対象となる個別墓地への公告看板を設置
官報に改葬公告を掲載する
3年間管理費の支払いのないお墓に対して、上記の手続きを踏んだうえで1年間申し出がなければ、墓地管理者は改葬を行うことができます。
とはいえ、無縁仏であることがわかったからといって、以下のような理由があり、1年が経過したらバンバン改葬を行うかというと、そんなことはありません。
無縁墳墓を解体するのに解体工事の費用がかかる
納骨されているお骨を永代供養墓に改葬する必要がある
事情を知ったご遺族が訪ねてきてトラブルになるかもしれない
疎遠になっていた親族が、何年も経過してから事情を知ってお墓を探して訪ねて来るケースは見受けられます。
実際にこんな事例もありました。
孤独死をされた方の親族が見つからず、やむなく自治体からの依頼で火葬を行い、親族もお墓もわからないので自治体や葬儀社と提携をしている納骨堂で安置をされていました。2年が経過した頃に、生前に疎遠になっていた息子さんが遺骨を探して納骨堂を訪ねてきたようなことがありました。
その時に既に合祀されているとトラブルになる可能性もあるので、一定期間は安置をする場合が多いのが現状です。
無縁仏があることによる墓地管理者に降りかかる問題
・石碑が倒壊する恐れがある
・管理費を受け取ることが出来ない
・雑草が伸びるなど墓地内の景観が悪化し新たなお墓が売れなくなる
・手入れされない植栽が伸びて根や枝が近隣のお墓に被害を与える
無縁仏が墓地内にあることは、収益の悪化や周囲の区画の所有者から苦情をもたらすなど、墓地管理者にとって大きな問題になります。
植栽が近隣の区画に被害を与える
一定以上の広さがあるお墓では、お墓を建てた時に墓所内に植木を植えることがよくあります。植えた時は小さな苗木であっても、お墓は数十年にわたって使用していく中で大木に育ってしまいます。大きく育った木の根が周囲のお墓の外柵を持ち上げてしまったり、石塔を傾けてしまうことさえあります。
切り倒すのも多額の費用がかかり大きな問題になります。
墓地内の景観の悪化
無縁仏の状態が長期にわたって続くと、墓石が傾いたり最悪倒壊する恐れもあります。
手入れがされなくなったお墓には、墓石は汚れ、雑草が伸びてしまったり見た目が悪くなってしまいます。植栽が伸びて隣のお墓にかぶさるようになったり、根が隣のお墓の外作を持ち上げてしまったりというトラブルも発生しています。
人の手が入らない場所にはハチが巣を作ったりクモの巣が出来たりと手入れされている墓所とは見た目も違ったものになってしまいます。
お墓が売れにくくなる
無縁仏は墓所の清掃や手入れがされずに放置されている為、見た目が悪くなってしまいます。外観から直接的に確認はできないかもしれませんが、長らくお参りに来ていないのだろうといういうのはすぐにわかります。
空き区画があったとしても、わざわざ明らかに管理されていないお墓の隣の区画は買いたくないでしょう。
お墓を買う方は墓地全体の管理状態にも目を配っていますので、管理体制に問題があるのでは?という印象にもつながりかねません。
墓地管理者の収益の悪化
しかしながら、墓地管理者にとっては無縁状態にあるお墓があるということは、本来受け取れるはずの「管理費」を受け取ることができず、管理費が未納になっているお墓が増えれば経営状況は当然悪化します。
いかにお寺や霊園は公共性が高いとはいえ、公営ではない以上、一定の収入がないと管理も何もできなくなってしまうのは民間企業と同じです。長い目で見ると運営の妨げになってしまう無縁墳墓をそのままにしておくのは得策ではありません。
そんな切実な事情がありますので、お墓を求めたい人からの問い合わせがあるにも関わらず、区画がいっぱいでお譲りすることができないような場合は、無縁墳墓を改葬して新しい区画として分譲を行うことで、永代使用料や新たな檀家さんからの管理費を受け取ることができます。
積極的に改葬を行うことはあまりありませんが、改葬を行うことで新たな墓地利用者(檀家さん)を得らえる可能性が高い場合、ストレートに言えば、解体費用などを払ってもそれ以上の永代使用料や管理費を得られる可能性が高い場合は実行されるというのが現実でしょう。
実際にお金をかけて改装の手続きに入った場合は、その後の利用目的が明確である可能性が高く、期間を過ぎると解体・改装が行われるものと思われます。
ご参考までに、一般的な改装公告はこんな感じです。
無縁墳墓等改装公告
〇〇〇〇〇〇〇のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することとなりますのでご承知おきください。
平成〇〇年〇月〇日
一、墳墓等所在地 東京都〇〇区〇〇〇〇
一、墳墓等名称 〇〇墓苑
一、死亡者の本籍及び指名 不詳
一、改装を行おうとする者 東京都〇〇区〇〇〇〇
もし、親族や縁者のお墓にこういった看板が立てられていたら、親族に連絡をしてあげてくださいね。
知らない間に不本意な改葬が実行されてしまった後では、元には戻らないので。
まとめ
お墓における無縁仏とは、事実上管理する人がいない状態のお墓のことを言います。
継承する人が生きていたとしても管理を放棄していたり、子供がいない状態で亡くなってしまうことによって表面化します。
放置されてしまったお墓は墓地管理において様々な問題が起こります。
これを防ぐために後継者がいないとお墓を購入することが出来ないような規約のある寺院や霊園が多くあります。
しかしながら、昨今の核家族化や少子高齢化とともにお墓が余ってしまう事態が起きています。
例えば、一人っ子同士が結婚すれば両家1基ずつお墓があることになり、二人子供がいたとしても姉妹であれば結婚後にお墓が余ってしまうことになります。
また、墓じまいをしたくても費用が高額になる為に事実上放置するしかないような事例も多く発生していくと考えられます。
若いうちからお墓のことについて知り、早めに対処を取れていればご先祖様をきちんと供養できる可能性が高まります。
まだ若いのに終活なんてなかなか考えないと思いますが、早いうちからお墓について考える機会を持って頂けると、無縁仏という問題は不正でいけるのではないかと思います。